「ダーツを毎回同じように投げたいけど、なぜか安定しない…」
カウントアップで、アベレージ60〜80前後で伸び悩んでいると、「いいスローがたまに出るのに、それが続かない…」とモヤモヤしますよね。
上達の大きな壁である、この「ダーツの再現性」。
そもそもダーツの「再現性」という言葉を知ってこの記事にたどり着く時点で、あなたはダーツを相当投げ込んできた方に違いありません。
それはとても素晴らしいことです!
この記事では、日本のトッププロである村松治樹選手が語る、再現性を高めるための本質的な考え方と具体的なコツを徹底解説します。
村松プロもまた、試行錯誤を繰り返す中で「最小限の動きで同じ結果を出す」という結論にたどり着いたと言います。
プロの知見から、自身のダーツを次のレベルへ引き上げるヒントを探っていきましょう。
村松治樹プロにとってのダーツの再現性を高めるコツ
この動画から、まずは村松治樹プロが語る、ダーツの再現性に関する考え方を要約してご紹介します。
村松治樹プロの「再現性」を支える考え方
- ダーツの再現性を高めるには、「無駄な動きをなくす」ことが何より重要。
- 完璧なフォームは不要。目指すべきは、自分にとっての再現しやすい「型」を見つけること。
- スタンスは右足に体重を90%かけるクローズドスタンスが基本。肩は的に対して垂直を維持。
- グリップは力を入れすぎず、腕でスイングし、指の関節を意識しすぎないこと。
- リリースは体に近い位置で早めに済ませることで、指に頼らないスローを実現。
- ブル以外のナンバーを狙う際は、腕の振りは変えず、腰の回転や高さだけで角度を調整する。
次からは、これらの考え方をより詳しく掘り下げて解説していきます。
無駄な動きをなくすことが再現性の鍵
村松プロは、再現性を高めるために最も重要なのは「無駄な動きをなくすこと」だと語っています。
「ダーツは3回同じことをすれば、同じ場所に飛んでいく」。
このシンプルな原則を達成するためには、スローにおける余計な動作を徹底的に排除することが不可欠と語っています。
例えば、テイクバックやリリースのタイミングが毎回異なると、スローの軸がブレてしまいます。
そうした不安定な要素を一つ一つなくしていくことで、スローはより安定し、毎回同じように投げられるようになっていきます。
結果として、自分にとって最もスムーズで、ブレにくい動きの「型」が見つかるようになるでしょう。
安定したスタンスで「ブレない軸」を作る
安定したスローは、安定したスタンスから生まれます。
村松プロは、クローズドスタンスで、右足に約90%の体重をかけることを基本としています。これは、体の軸を固定し、スローを安定させるためです。
なぜ体重を片方の足に集中させるのかというと、軸足がしっかりすることで、腕の振りだけに集中できるようになるからです。
両足に均等に体重をかけてしまうと、重心が左右にブレやすくなり、スロー全体が不安定になってしまいます。
また、村松プロはボードの中心に足の生えているところ(脛骨)が来るように立つことで、ダーツを投げるまでの距離を最短にしています。
フォームが安定しないと感じる方は、まず自分のスタンスを見直し、どっしりとブレない軸を作るところから始めてみましょう。これが再現性を高めるための最初のコツです。
スタンスについては、当ブログのダーツの投げ方が安定しないからスタンス(立ち方)を変えてみた結果でより詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。
利き目を活用した「正確な構え」の基準
村松プロは、右目が利き目であるため、右目とダーツのフライト、ボードの的が一直線になるように構えています。
これは、的を見るのではなく、自分の利き目を基準にすることで、曖昧さをなくし、毎回同じように構えるための「型」を作るためです。
的がどこにあるかよりも、自分の構えの基準がどこにあるかを意識する方が、再現性は格段に高まります。
構えが毎回違うと感じる方は、利き目を意識した自分なりの基準を作ってみると良いでしょう。
グリップは「力を入れず」に握るくらいで、指を意識しすぎない
ダーツを強く握りすぎると、手首や指の関節が硬くなり、スムーズなリリースができません。
村松プロは、ダーツを力を入れずに握り、指の関節を意識しすぎないことを心がけています。
また、村松プロのスローは、親指を深めに、人差し指を浅めにして自然な左回転をかけていますが、
たくさんある指の関節を意識しすぎると、指に頼って不自然なスローになるため、適度な力加減を保つことが重要だとも語っています。
グリップの力加減を意識するだけで、スローの感覚は劇的に変わり、毎回同じように投げやすくなります。
スローを安定させる「早めのリリース」
リリースが遅いと、ダーツは手の中で余分な動きをしてしまい、狙った場所からズレやすくなります。
特に、人差し指や中指でダーツを「弾く」ような動きは、再現性を著しく低下させます。
村松プロは、再現性を追求するために、ダーツをなるべく体に近い位置で、早めにリリースすることを心がけています。
「早めのリリース」を意識することで、指の操作に頼りすぎることがなくなり、より自然な腕の振りが可能になります。
具体的には、テイクバックの頂点から、フォロースルーへと向かう一連の流れの中で、ダーツを「投げる」のではなく、「肘から先をスムーズに伸ばすことで、自然にダーツが手から離れていく」ようなイメージを持つと良いでしょう。
これにより、余計な力が抜け、ダーツがより安定した軌道を描くようになります。
腰で回転と高さ調整をしながら的を狙う
ブルだけでなく、様々なナンバーを狙うとき、毎回スタンス(立ち位置)やフォームを変えてしまうと、スローの軸がブレてしまい、再現性が低下します。
フォームや立ち位置を毎回変えることは、毎回違うダーツを投げることと同じです。
村松プロは、狙う場所が変わっても、腕の振り方や指の使い方は変えません。
的を捉えるための角度調整は、「腰の回転だけ」で行います。
スタンス(立ち位置)を大きく変えずに、腰の向きをほんの少し変えるだけで、スローの軸をブレさせることなく、様々な場所を狙うことができるのです。
まずは20番、19番、18番といった隣り合うナンバーを、立ち位置を変えずに腰の回転と高さ調整だけで狙い分ける練習から始めてみましょう。
以上から、村松治樹プロは、ダーツの再現性を高めるために、できるだけ無駄な動きを排除、あるいは固定化することで、3本を同じように動作させるためにフォームを洗練させてきたのです。
ダーツの再現性を加速させるためのヒント
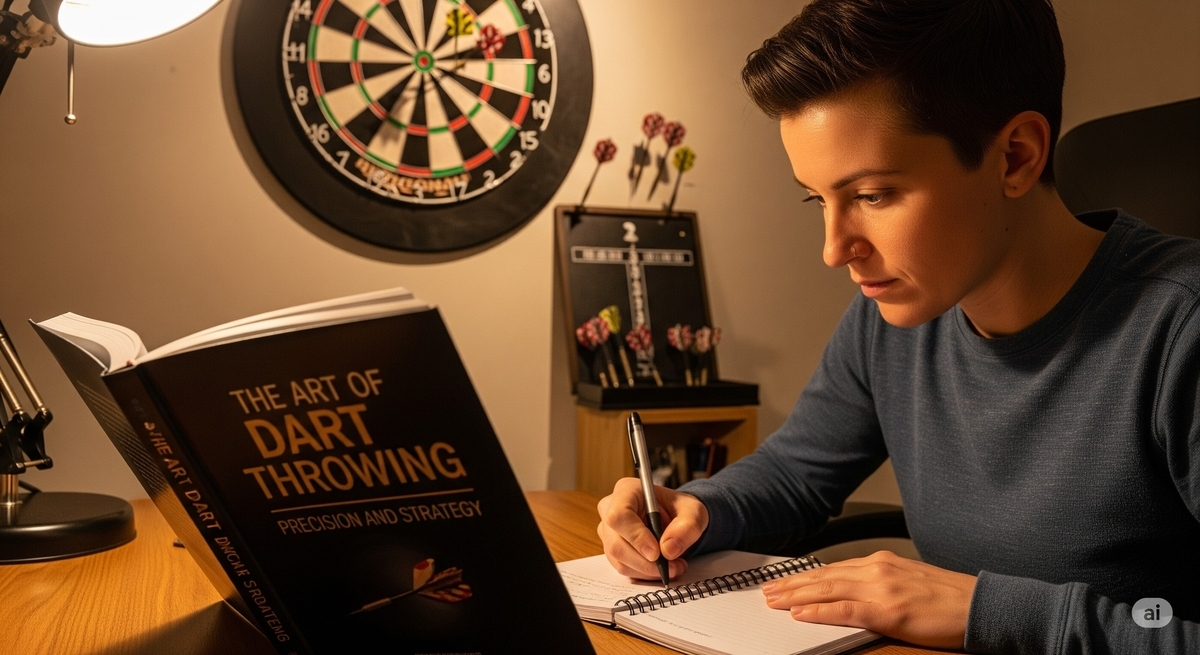
成功したスローをスマホやメモ帳に「言語化」する
Bフライトでも、たまに「完璧なスロー」が出ることがありますよね。
その「たまたま」を「必然」に変えるための方法が、スローをスマホやメモ帳に簡単でいいのでできるだけ「言語化」することです。
成功したスローが出た時、漠然と「よかった」で終わらせず、その時の感覚を具体的に言葉にしてスマホやメモ帳に書き留めてみましょう。
- 「グリップにほとんど力が入っていなかった。ダーツが軽かった」
- 「テイクバックがいつもよりスムーズで、肘から先に引っかかりがなかった」
- 「ダーツが手から離れる瞬間が、いつもより早かった気がする」
など、言語化を繰り返すことで、「成功スロー」、「失敗スロー」の共通点が自分のデータとして蓄積され、次のスローに活かすことができるのです。
このメモは、不調の時に「いつもの良い感覚」を思い出すための強力な助けにもなります。
友人とのプレイで試せる「動画」を活用した振り返り方
自分のフォームを客観視することは、再現性を高める上で非常に重要なコツです。
スマホのカメラで自分のスローを横や後ろから撮影してみましょう。
録画した映像を友人やダーツ仲間と一緒に見返すと、自分では気づかなかった力みや、肘のブレ、手首の角度の変化など、改善すべきポイントが明確になります。
特に、上手くいったスローと失敗したスローを並べて比較することで、両者の違いがよりはっきりとわかります。
上手くいったスローのフォームを真似して繰り返し投げることで、良い感覚を身体に覚え込ませることができます。
村松プロもまた、日々試行錯誤を繰り返しながら、自分に合った投げ方を模索しています。
この記事を参考に、あなただけのスタイルを見つけるプロセスを楽しんでみませんか?
【PR】TARGET JAPAN RISING SUN G9(ライジングサン ジェネレーション9)
リアグリッププレイヤーのために開発された村松プロの最新シグネチャーモデル。手に吸い付くようなフォルムが優れたホールド感を提供し、シリーズで受け継がれてきたリアグリップに最適な形状を継承しています。
画像引用元: ダーツハイブ (https://www.dartshive.jp/)
本記事は、ダーツの再現性に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の製品の効果を保証するものではありません。ダーツ用品の選択は、個人のプレースタイルや好みに合わせて行うことを推奨します。
こちらも読まれています
・プロも実践!ダーツのリリースが安定しない人のための再現性アップ術
・ダーツが刺さらない・弾かれる理由をやさしく整理|原因と改善のヒント
・【15選】ダーツの横ブレ(横ズレ)|左右にブレる原因と改善方法



